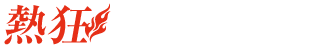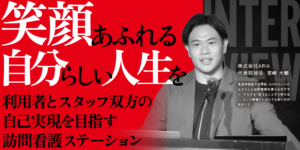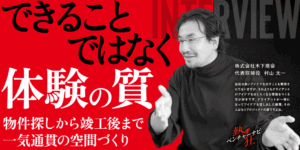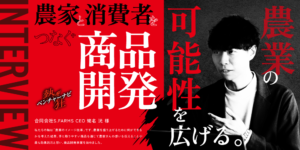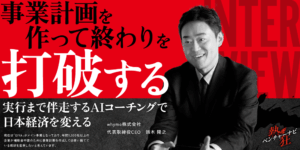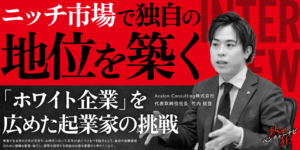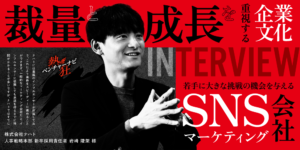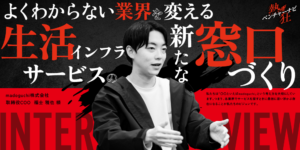【代表インタビュー】株式会社Massive Act 代表取締役 高萩 遼介(Ryosuke Takahagi)
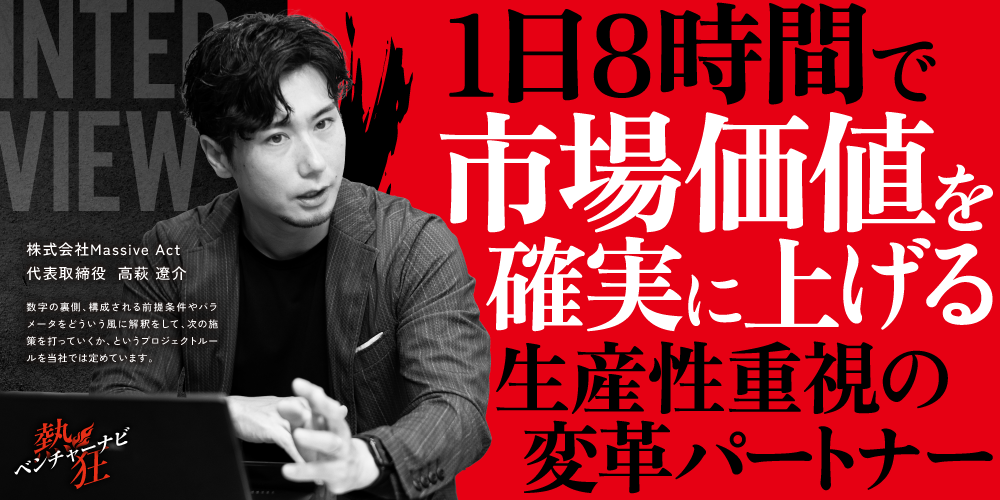
メンバードリブン経営で実現する、持続可能な企業成長の新モデル
デジタル変革が叫ばれる中、多くの企業が真の変革を実現できずにいる現状があります。マーケティング施策の断片化、DX推進の停滞、そして何より「人」を置き去りにした成長戦略。
そんな中、「変革の起点を創る」をミッションに掲げる株式会社Massive Act。代表取締役の高萩 遼介(Ryosuke Takahagi)さん(以下、高萩さん)は、設立以来8期連続増収増益という驚異的な成長を実現し、英国Financial Times社の「アジア太平洋地域急成長企業ランキング」で3年連続ランクイン、広告・マーケティング部門では日本国内1位を獲得しているマーケティングコンサルティングファームの経営者です。
「メンバードリブン経営」という独自の経営哲学のもと、社員満足度を源泉とした価値提供を最優先に据えながら高品質なサービスを提供し続ける同社。外資系コンサルファーム出身の高萩さんが目指す、新時代の企業変革支援について、その革新的な取り組みを伺いました。
プロフィール

株式会社Massive Act
代表取締役 高萩 遼介(Ryosuke Takahagi)
趣味
キックボクシング、筋トレ、アスレチック
尊敬する人
自分と関わっている人全員
座右の銘
知行合一
学生が読むべき本
「企業参謀」大前 研一
経営者におすすめの本
「成功者の告白」神田 昌典
人生で一番熱狂したこと
いつでも
川上から川下まで一気通貫で支える変革パートナー

デジタルマーケティングとDX支援の二本柱
小川:御社の事業内容を教えてください。
高萩さん:当社はデジタルマーケティング支援とDX支援の二本柱で事業を展開しています。デジタルマーケティングでは、新規プランニングから実行、検証までを一貫して提供しており、新規獲得からLTV(生涯顧客価値)を高めるための一連の活動を支援しています。
DX支援に関しては、データ統合だったり、サイロ化しがちなお客さまの企業資産を統合した既存事業の改善や、次のビジネス展開に活かしていくサポートをさせていただいています。分かりやすい有形のサービスなどではなく、クライアント課題に応じたオートクチュール型のコンサルティングが中心です。
圧倒的な品質へのこだわりが生む差別化
小川:そうしたデジタルマーケティングとDX事業で、他社との違いや特徴はどこにあるのでしょうか?
高萩さん:デリバリー、つまりお客さまへのアウトプットや成果物の提供プロセスにおいて、期待要件と品質に強くこだわっていて、それが差別化要素としてお客さまからご評価いただいています。たとえば、数字の解釈1つとっても、各社によってその捉え方や優先度付け、実行方針に大きな違いが生まれます。
小川:数字の解釈において、御社ではどのような基準を設けているのですか?
高萩さん:数字の裏側、構成される前提条件やパラメータをどういう風に解釈をして、次の施策を打っていくか、というプロジェクトルールを当社では定めています。私が以前在籍していた広告会社やコンサルファームの水準よりも少し厳格なボーダーラインを設定しているんです。
最小粒度まで意味合いや意義を追求するスタンスですね。勿論、すべてに局所的に時間を投下するということではなく、ある事象やアジェンダを課題のセンターピンとして仮定した場合に、一気にDeep Diveするイメージです。そういったことを細かいスパンで繰り返し検証・実行をしています。
小川:具体的にはどのような部分でその品質の違いが現れるのでしょうか?
高萩さん:たとえば資料一つ、コミュニケーション一つとっても、基本的には絶対に仮説を立てる、事実だけでなく事実と仮説をセットで必ず言う、などといったチェックリストを設けて、全員が均質的な動きをできるように弊社ならではのワークスタイル、デリバリー基準を定めているのが大きな特徴ですね。
前職での苦い経験から生まれた「メンバードリブン経営」

コンサルファーム時代の気づきと起業への転機
小川:そうした高い品質へのこだわりは、高萩さんのご経歴と関係があるのでしょうか?
高萩さん:新卒で入社したデジタルエージェンシーでアカウントプランナーを8年ぐらいやっていました。そこでグループMVPやベストマネージャー賞、連続達成記録の樹立などといった実績を上げることができました。
小川:素晴らしい実績ですね。その後コンサルファームに転職されたのはなぜでしょうか?
高萩さん:次のスキルを身につけたいと思ったからです。当時、日本企業が「失われた20年」といわれる長期的な経済低迷からの脱却を図る中、旧来システムの刷新に合わせてデジタル変革、トランスフォーメーションの必要性が叫ばれ始めた頃です。その黎明期の中で、クライアントの事業データまで入りこむコンサルティングファームに着目しました。その黎明期に、DXを推進する新設部署に参加しました。
小川:その会社での経験はいかがでしたか?
高萩さん:コンサルでは、より中長期的な視点でクライアントの経営課題に取り組むという、非常に本質的かつ戦略的な仕事に携わらせていただきました。一方で、私自身はもともとネット広告やデジタルマーケティング領域で、リアルタイムなデータを活用しながら短いスパンでPDCAを高速に回すスタイルに慣れていたため、最初はそのギャップに戸惑いもありました。
しかし結果として、この両極とも言えるスタイル・視点を経験したことで、戦略構築の精度と実行フェーズでのスピード感、双方の重要性をバランスよく捉えられるようになりました。今では、短期成果と中長期の事業成長を両立させる視点で、より価値の高い提案・実行ができるようになったと感じています。
起業への想いと消去法的な決断
小川:そうした経験が起業のきっかけになったのですか?
高萩さん:「起業して世の中を変えてやるぞ」というマインドはあまりなくて、本当に目先や足元をみて、「自分にできること」で立ち上げたのがスタートでした。意外と消去法に近いかもしれません。
小川:現在振り返ってみて、当時の経験はどう活かされていますか?
高萩さん:今は当時向き合っていたような大手企業様にもご支援させていただいており、コンサルで学んだ虫瞰と鳥瞰、具体と抽象、短期と中長期、その両軸の視点でプロジェクトを推進しています。当時の経験があったからこそ、プロジェクトの進め方や考え方が今に活きていますね。
いま振り返ると、あの経験が自分の中に確かな「型」として残っていて、提案の構造化やステークホルダーとの合意形成といった場面で大いに活きています。
結果として、スピード感を大切にしながらも、クライアントが求める品質やプロセスを担保できる自分になれたと実感しています。
新卒時代の圧倒的な「量」への熱狂

走り抜けた20代で得た、「仕事力の基礎」
小川:高萩さんご自身の経験で、特に熱狂された時期はいつ頃でしょうか?
高萩さん:現在進行形で熱狂していますが笑、多分一番熱狂したのは新卒から5年ぐらいです。本当に昭和世代的な働き方で、毎朝4時くらいまで残業は当たり前、会食や飲み会のあとも当然のごとく会社に戻って仕事したり、週2~3日はオフィスに寝泊まりというような生活を送っていました。
小川:そこまでのめり込まれた理由は何だったのでしょうか?
高萩さん:正直なところ、「仕事にはまってしまった」という表現が一番近いですね。ふとした瞬間に、「いま自分が休んでいる間にも、誰かは前に進んでいる」と感じてしまって。そんな焦りもあり、土日も関係なく働いていました。
もちろん当時は、確信があったわけではありません。ただ、急成長している市場で努力を積み重ねれば、いずれ自分の力になるはずだという、根拠のない信念のようなものは持っていました。
よく「量質転化の法則」と言われますが、まずは圧倒的な量をこなすことで、自然とアウトプットの質が上がってくる。そのサイクルを早く回したい一心で、手を止めずに走り続けていた感覚です。
小川:その時期に学んだことで、現在に活かされていることはありますか?
高萩さん: 変化の激しい業界で過ごした経験は、今の自分の基盤になっています。当時のインターネット広告業界は、たとえばYahoo!の純広告(バナー掲載)が1週間で3,000万円といった大胆な予算規模が動く世界で、成果を左右する変数も非常に多かった。もちろん、そのあとに運用型広告に市場がシフトしていくのですが、より変数と変化が大きな時代になっていきました。
そうした中で、プランニングから提案、運用、改善までを一気通貫で担わせてもらえたのは非常に大きな経験でした。若手のうちからお客様と直接向き合い、意思決定の近くで動けたことで、スピード感と責任感を持ってPDCAを回す姿勢が自然と身につきました。今も、そうした視点はあらゆるプロジェクトの土台になっています。
セレンディピティの重要性
小川:そうした経験を踏まえて、若い世代にアドバイスはありますか?
高萩さん:私が大事にしているのは「セレンディピティ」、つまり「偶発的な出会いや発見」の価値です。
一見すると無駄に思える経験が、後になって大きな意味を持つことがある。スティーブ・ジョブズの「Connecting the dots(点と点が後から線になる)」という言葉がまさにそれで、私自身も、そうした「後からつながった経験」に何度も助けられてきました。
今の時代、SNSのアルゴリズムによって、自分が興味のある情報ばかりが流れてきます。でも、本当に自分を成長させてくれるのは、意図しなかった出会いや、興味の外側にある情報だったりします。だからこそ、あえて興味のないことにも触れてみる。偶然を歓迎する姿勢を持つことが、長い目で見れば自分のキャリアや可能性を大きく広げてくれると信じています。
市場価値を確実に上げる働く環境

残業代1分から支給する生産性重視の文化
小川:実際に働く環境について、どのような特徴があるのでしょうか?
高萩さん:当社のカルチャーをひと言で表すなら「本質的な生産性にこだわる組織」だと思います。
一般的な同業他社では、月45〜60時間の「みなし残業」が常態化しているケースもありますが、当社では1日8時間勤務が原則で、残業代は1分単位で全額支給しています。
つまり、同じ年収でも他社よりも年間で2〜3ヶ月分少ない稼働時間で働ける設計になっている。加えて、業界平均よりも高い水準の給与を提示している分、1時間あたりのアウトプットには非常に高い基準を求めています。
その分、思考力・設計力・推進力のすべてにおいて密度の高い仕事が求められ、それがそのまま市場価値としての強さに直結する。私自身も「ここで力をつけた人材はどこでも通用する」と自信を持って言える環境です。
高い生産性を支えるワークスタイルルール
小川:そうした環境で、どのような働き方をされているのですか?
高萩さん:当社では、高い生産性を支えるためのワークスタイルやコミュニケーションのルールを、細かく設計し、文化として根付かせています。
たとえば、「未読スルーはしない」「◯分以内に簡易でもレスを返す」「提案時には事実(ファクト)と自分の仮説・考察を明確に分けて伝える」といった、ビジネスにおいて本来「当たり前であるべきこと」を徹底しています。これらは単なるルールではなく、再現性ある成果を生むための型として機能しています。
小川:そうした環境に合う人、合わない人の特徴はありますか?
高萩さん:結局のところ「性格の良さ」と「オーナーシップ」がすべてだと思っています。他責にせず、誰かを攻撃したり陰口を言わない人。たとえ愚痴があったとしても、それは「ガス抜き」にとどめ、建設的な方向に切り替えられる人。
そして何より、自分の仕事にオーナーシップを持てるかどうかが大きいですね。たとえば「今日は思ったように成果が出せなかった」と感じたら、会社に言われる前に自分で振り返り、翌日には自ら改善アクションを取れる。そういった人は、この環境で圧倒的に伸びますし、間違いなく強くなっていきます。
集中できる環境と家族との時間の両立
小川:実際のオフィスの雰囲気はいかがですか?
高萩さん:一言で言うと、「集中に最適化された環境」ですね。目的志向の高いメンバーが多く、業務に必要な会話や相談は活発に行われますが、いわゆる雑談のようなコミュニケーションは少ないかもしれません。
小川:それは課題と感じられているのですか?
高萩さん:バランスという意味では、もう少し余白があってもいいかなと思うこともありますが、「短時間で成果を出す」という観点では非常に合理的な環境だと思います。
特に家庭を大事にしたい方や、プライベートの時間も大切にしたい方にとっては、無駄な時間が少ない分、非常に働きやすいはずです。私自身も、子どもの行事にはしっかり顔を出しますし、そうしたライフスタイルをチーム全体で尊重し合えるのも、当社らしさのひとつだと思います。
性善説に基づくプロフェッショナルファームへの展望

リスペクトで形成される組織文化
小川:今後、どのような会社にしていきたいとお考えですか?
高萩さん:基本的には高生産性のパフォーマー集団にしていきたいというのが大前提ですが、もっと定性的に言うと、リスペクトで形成されたプロフェッショナルファームにしたいんです。互いに敬意を持って関われる関係性を大切にしながら、信頼と前向きな空気感が循環するような組織をつくっていきたいと思っています。
小川:そうした組織づくりの背景には、以前の起業経験があるのでしょうか?
高萩さん:そうですね。1社目を立ち上げた当初は、短期的な成果や利益を追いかけることに意識が向いてしまい、結果的に組織としての一体感や継続的な関係づくりが疎かになってしまった部分がありました。
そうした経験を通じて、「誰と、どのように働くか」の大切さに気づかされ、今の経営スタイルにつながっています。
AI時代に求められる人材とMassive Actの使命
小川:現在の経営方針と事業的な展望について、どのようにお考えですか?
高萩さん:当社では「メンバードリブン経営」を掲げ、制度や仕組みの設計だけでなく、組織運営の意思決定にもメンバーの声を積極的に取り入れています。結果として、全員が同じ方向を向きながら自律的に動ける状態が実現できており、組織内の軋轢や不協和音が極めて少ないのも特長です。
事業としては、AIが加速度的に進化する時代だからこそ、「人間にしかできない価値」を磨く必要があると感じています。中でも、構造化思考をもとに他者を巻き込みながら物事を動かす「ディレクション力」や、最後までやり切る「推進力」といったポータブルスキルは、今後ますます重要になります。そうした人材を育てられる組織でありたいし、そうした人たちが活躍できる環境を整えていきたいと思っています。
小川:最後に、どのような方と一緒に働いていきたいと考えていますか?
高萩さん:まず大前提として「性格がいい人」ですね(笑)。これは冗談のようでいてすごく大切で、他者をリスペクトできること、自分だけでなくチームや顧客の成果を真剣に考えられることが、私たちのカルチャーでは最重要視されています。
そのうえで、自分のアウトプットに対して常にオーナーシップを持ち、たとえば「今日は納得できる価値を出せなかったな」と思ったら、翌日には自ら改善に動けるような方と一緒に働きたいです。
あとは、常に120%、130%を目指そうとする向上心。与えられたものをこなすのではなく、自ら意味を問い、挑戦していける姿勢を持った方に来ていただけたら嬉しいですね。
私たちは「変革の起点を創る」というミッションを掲げていますが、これは単にクライアント企業に対してだけでなく、メンバー一人ひとりが「自分自身の変革の起点」となれるような組織を目指しているという意味でもあります。
企業変革の最前線で、思考と実行の両輪で挑みたい方──ぜひ一緒に、面白い未来を創っていきましょう。
会社概要
| 法人名 | 株式会社Massive Act |
| HP | https://massive-act.com |
| 設立 | 2017年2月 |
| 事業内容 | デジタルマーケティング支援事業 DX導入/コンサルティング/アドバイザリー事業 グロースマーケティング事業 マーケティングオペレーション構築支援事業 |
| 採用情報 | https://massive-act.com/recruit |
※本ページは2025年5月15日時点の情報です。