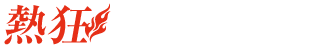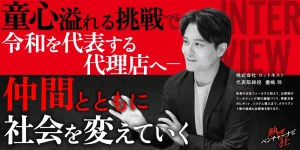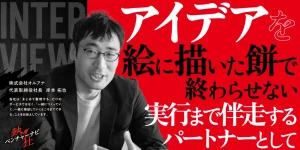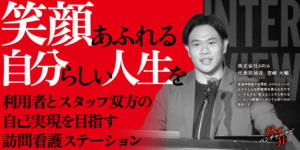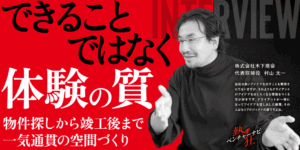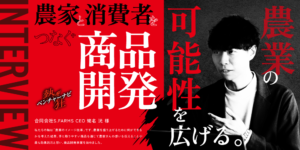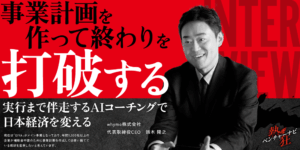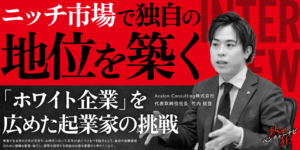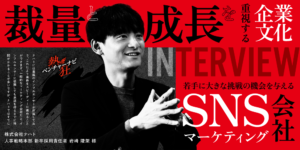【役員インタビュー】madoguchi株式会社 取締役COO 福士 雅也
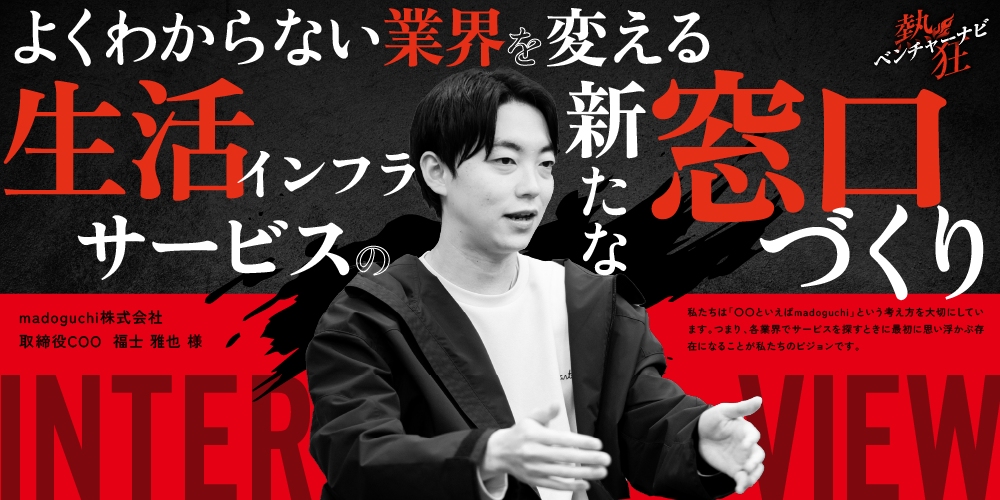
不用品回収、ハウスクリーニング、害虫駆除など、生活関連のサービスを探すとき、多くの人が「どこに頼めば良いのか分からない」という悩みを抱えています。一方で、こうしたサービスを提供する業者も、過剰な価格競争や悪徳業者の存在により、安定した経営が難しい状況にあります。
madoguchi株式会社は、こうした「よくわからない業界」に新たな仕組みをつくり、ユーザーと業者の双方にメリットをもたらすプラットフォームの構築に挑戦しています。一括見積もりサイトとして始まった事業は、現在では即時対応型のマッチングアプリ「オヨビー」へと発展。創業10年目を迎え、今後の事業拡大を見据える同社の取締役COO福士 雅也さん(以下、福士さん)に、事業内容や将来の展望について話を伺いました。
プロフィール

madoguchi株式会社
取締役COO 福士 雅也
趣味
ビジネス映画鑑賞、サイクリング
尊敬する人
安岡 尚和(madoguchi株式会社 代表)
座右の銘
成功はみんなのおかげ、失敗は自分のせい
学生が読むべき本
「大富豪アニキの教え」丸尾 孝俊
人生で一番熱狂したこと
誰もが当たり前に使うサービスを、自分たちの手でゼロから形にしていくことに熱狂しています。
誰もが安心して使える窓口をつくる

 小川
小川御社の事業について教えてください。
福士さん:私たちは大きく2つの事業を展開しています。
1つ目は「Webメディア事業」です。リユースや不用品回収、ハウスクリーニング、害虫駆除など、生活に関わる業界に特化した一括見積もりサイトを運営していて、ユーザーさんはその中で業者さんを比較し、選ぶことができます。一方で、業者さんはmadoguchiのメディアに掲載すれば、Webから安定的に集客できる仕組みです。
2つ目は「アプリ事業」です。今年からスタートした事業なのですが、Uberのような仕組みで、エアコン修理やハウスクリーニングなどをすぐ呼べるサービス「オヨビー」を提供しています。ユーザーさんはアプリ上で見積もりし、金額が合えばすぐ依頼できる仕組みになっています。
 小川
小川他社との差別化ポイントについてもお聞かせください。
福士さん:私たちの最大の差別化ポイントは、「ユーザーの選択負担を減らすこと」と「業者側の利益確保」の両立、そして「営業力」にあります。
ユーザー視点では、不用品回収などのサービスを探す際、「ここに頼めば間違いない」という代表的な存在がないため多くの方が検索からはじめます。そこでさまざまな業者さんから選ぶのは知識がない状態では大変です。他社サイトでも業者一覧の表示はありますが、選択肢が多すぎて迷ってしまいます。
私たちのサービスは、ユーザーが簡単に情報を入力するだけで、事前審査済みの信頼できる業者さんから最適なマッチングを自動で行います。これにより「このサービスに頼んでおけば安心」と思っていただける環境をつくっています。
業者側の視点では、私たちの最大の強みは営業力です。他のプラットフォームでは料金の安さや口コミ数で上位表示される仕組みのため、業者さんは利益を削って価格競争せざるを得ません。私たちは業者さんとの強固な関係構築にこだわり、一日に数百社と連絡を取り合うこともあります。その結果、業者さんが適正価格で利益を確保しながら持続的に成長できる環境を提供できています。
この営業力こそが、同じビジネスモデルを模倣されても簡単には真似できない私たちの真の差別化ポイントだと考えています。
 小川
小川福士さんご自身は、どのような経緯でこの会社に参画されたのでしょうか?
福士さん:もともと私は典型的な大手志向でした。大学入学時から「大手企業に行くだろう」と思っていましたが、社会人経験なしで就職するのは不安だったので、大学2年後半にインターンを探しはじめました。
最初に参加したインターンは多くの学生が集まる楽しいイベント型でしたが、私が求めていたのは純粋な「社会人経験」でした。そこで少人数で実務に関われる環境を探し、今の会社に出会いました。
当時は社長と社員1人、事務員さんの3人体制。面接を受けて入社したのですが、驚いたことに2週間後にその社員が退職し、事務員さんも産休に入ったため、気づけば社長と私の二人だけという環境に。大学3年の途中からは大手の就活も並行して行い、内定もいただきました。
ただ就活を通じて違和感を覚えたのは、多くの方が「ここで出世するため」「将来の起業のため」など、人生設計を逆算して会社を選んでいる点でした。一方、私はこの会社で「このサービスをもっと良くしたい」「そのために必要なスキルを身につけたい」と考えながら働いていて、自分にはそちらの方が自然でした。
最終的に大学4年の4月、大手の内定を辞退してこの会社で働くことを決断しました。入社後半年で不用品回収領域を自らみつけて提案する機会もあり、サービス視点で考え、会社と共に成長していく環境が自分に合っていると確信しています。
ユーザーの負担を減らし、業者の利益を確保する

 小川
小川業者さん目線で「オヨビー」を利用するメリットはどのようなことがありますか?
福士さん:「オヨビー」の最大の特徴は、業者さんとユーザーさんの双方にメリットがある設計になっている点です。
多くの業者比較サイトでは、業者さんは上位表示されるために料金を極限まで下げざるを得ません。一時的に上位表示されても、また新たな業者さんがより安い価格で参入してくるため、業界全体の相場がどんどん下がり、結果として業者さんの利益が圧迫される悪循環が生まれています。
私たちの「オヨビー」では、成約手数料型のビジネスモデルを採用しています。業者さんは売上の一部を手数料として支払う形なので、初期費用や固定費のリスクがなく参加できます。さらに「メディア事業」で既に取引のある信頼性の高い業者さんが多く参加しているため、サービス品質も一定水準以上を保てています。
また、従来のプラットフォームと大きく異なる点として、業者さんと私たちの利害が完全に一致する「売上折半」の仕組みを導入しています。これにより、単なる集客ツールの提供ではなく、「一緒に市場を良くする共同体」としての関係性を構築できています。
私たちは単に集客の場を提供するだけでなく、業者さんが安定して質の高いサービスを提供し続けられるよう、営業力やマーケティング、組織づくりの面でも伴走支援しています。「業者さんを良くすること=市場を良くすること」という考えのもと、適正価格で持続可能なビジネスを実現するエコシステムをつくり上げたいと考えています。
 小川
小川他社との差別化の中で営業力が強みというお話がありましたが、その営業力を高めるためにどんな取り組みをされてきたんですか?
福士さん:特に取り組んできたことは、3つ挙げられます。
まず1つ目は評価制度とインセンティブ制度。保険業界や不動産業界を徹底的に研究して、自社にフィットする形にカスタマイズしました。成果を出した分だけ自分の給与にしっかり反映される仕組みにしているので、社員は自分の数字に本気で向き合える。会社・社員・業者さん、三方の利益が一致する状態を意識して設計しています。
2つ目はカルチャー形成。採用段階から、徹底的にこだわりました。まだ社員が数名しかいない頃から人事部を立ち上げて、普通のベンチャーなら3次選考くらいで終わるところを、人によっては4次、5次までやります。そういった過程を通して、結果的に「競い合う文化」や「チームで成果を出す文化」がしっかり社内に染みついたのは良かったなと感じています。
3つ目は、行動の徹底管理と密なコミュニケーションです。私たちは社員が3人しかいなかった時代から、CRMツール(Salesforce)を活用して、一人ひとりの営業行動をしっかり管理してきました。それに加えて、毎日帰る前には必ず10分〜15分ほど面談をして、「今日どうだったか」「明日はどう動くか」を確認する時間を設けています。これは新卒に限らず、2年目、3年目の社員に対しても同じで、直属の上司と密にコミュニケーションを取っています。
こうした取り組みのおかげで、新卒の段階から「自分はすぐに戦力になれている」という実感を持てる環境が自然とできあがっていると思います。
 小川
小川なぜそこまで「チーム」や「営業力」にこだわったのでしょうか?
福士さん:このこだわりの背景には、創業メンバーの苦い経験があります。代表も私も、過去に「個人プレーが重視される」「深夜まで働くのが当たり前」といった厳しい環境で働いた経験があります。
そこでは人がどんどん離れていき、事業の持続的な成長も難しい状況でした。その経験から「個々人がバラバラに頑張るだけでは、組織としての限界がある」という教訓を学びました。
だからこそ、私たちは会社の方針として「リモートワークはしない」「必ず対面でチームとして戦う」ということを創業期から決めていました。これは単なる古い働き方への固執ではなく、特に私たちの業界では、人と人の信頼関係が何よりも重要だと確信しているからです。
実際、業者さんとの関係構築にしても、対面でしっかりコミュニケーションをとることで信頼関係が生まれ、長期的なパートナーシップにつながっています。社内でも、リアルな場での密なコミュニケーションを通じて、一人ひとりの力を最大限に引き出せる組織づくりを心がけています。
このチーム主義のアプローチが、結果的に業界特有の課題解決にも効果を発揮していると実感しています。
「よくわからない業界」を変える取り組み

 小川
小川業界内で課題に感じている点はどんなところですか?
福士さん:この業界特有の課題は、主に外的要因と内的要因の両面から生じています。
外的要因としては、悪徳業者の存在が業界全体の信頼性を低下させている点が挙げられます。たとえば「ぼったくり業者がニュースで取り上げられた」というだけで、真面目に取り組んでいる業者さんまでお客様を失うことがあります。また、業界の相場が不透明なため、ユーザーさん自身も「適正価格かどうか」を判断しづらい状況があります。
私の友人でも、家のリフォームで明らかに高すぎる金額を請求されていたケースがありました。相場を知らないと、提示された金額をそのまま支払ってしまうんですね。実はこうした「気づかないぼったくり」が多いのです。
内的要因としては、多くの業者さんが個人事業主や小規模な会社であるため、組織としての基盤が脆弱であることが挙げられます。たとえば「従業員による売上の持ち逃げ」といった問題が日常茶飯事のように起こります。また、多くの業者さんは「その日暮らし」の状態で、長期的な顧客関係の構築や再販戦略といった発想がなかなか根づきません。
これらの根本的な課題を解決しない限り、ユーザーさんの満足度も継続的に向上していきません。だからこそ私たちは、単にメディアやアプリを運営するだけでなく、「業界全体をどう健全化していくか」という視点で事業を展開しています。
業者さんの経営基盤を強化し、適正価格でサービスを提供できる環境を整えることで、結果的にユーザーさんにも安心して利用いただける市場をつくっていきたいと考えています。
 小川
小川アプリ事業「オヨビー」では、どのような特徴や強みがあるのでしょうか?
福士さん:「オヨビー」の強みとして特に注目していただきたいのは、金額の透明性と圧倒的なスピード感です。
まず金額の透明性についてですが、この業界の大きな課題の一つに「料金相場の不透明さ」があります。「オヨビー」ではこの問題を解決するために見積もりシミュレーターを組み込んでいます。ユーザーさんはアプリ上で自分で金額を事前に決めることができ、その金額で対応可能な業者さんとだけマッチングする仕組みです。つまり、「いくらかかるかわからない」という不安を完全に解消し、納得した金額でサービスを受けられるようになっています。
次にスピード感ですが、従来のフローを考えてみましょう。たとえばエアコンの水漏れが発生した場合、まず業者を探して連絡し、日時を調整し、現地で見積もりを取り、金額に納得できなければまた別の業者を探す、といった具合に、手間と時間がかかります。特に夏場などの繁忙期には「3週間後にしか対応できない」といったこともよくあります。
「オヨビー」なら、最短4分で業者さんとマッチングし、チャット機能で日時調整をした後、即日対応も可能です。エアコンの水漏れであれば、依頼から1時間半程度で修理完了することも珍しくありません。
この「透明性」と「スピード」という二つの強みにより、ユーザーさんの「困った」をすぐに解決できる画期的なサービスとなっています。また、アプリ上での決済なので現金取引も不要、結果としてぼったくりのリスクも排除できています。
 小川
小川アプリ事業は今年立ち上げられたばかりとのことですが、集客や認知拡大において、特に意識していることは何ですか?
福士さん:アプリ事業の最大の課題は「必要なときに思い出してもらえるか」という点です。
Web集客とアプリ集客には根本的な違いがあります。Webメディアの場合、「不用品回収」などの明確なキーワードで検索した人に広告を出せるので、「今すぐ必要としている人」に直接アプローチできます。
一方、アプリは違います。ユーザーの行動属性に基づいて配信されるため、「アプリをダウンロードしたからといって、すぐに依頼につながるとは限らない」という特性があります。
たとえばメルカリなどのフリマアプリは、ダウンロードすれば即座に「物を売って稼げる」というメリットがあります。しかし「オヨビー」は「困ったときに使う」サービスなので、ダウンロードしてから実際に使うまでに時間差が生じるケースが多いのです。
そのため、私たちは2つの側面から取り組みを進めています。1つは継続的な広告展開による認知拡大。もう1つは「困ったときに思い出してもらえる」ためのブランディング活動です。
具体的には、タレントの鈴木愛理さんを起用した大規模なキャンペーンも展開しています。これはWeb広告だけでは届かない層にまでリーチする試みで、「困ったときに思い出してもらえる」というブランド構築を目指しています。
また、メディア事業で培った1000社以上の業者ネットワークが、アプリにおいても大きな強みとなっています。アプリ立ち上げから2ヶ月で1000社の業者さんに参加いただけたのは、これまでの信頼関係があったからこそです。
ユーザーさんへの価値提供と同時に、業者さんにとっても「ノーリスクではじめられる」プラットフォームであることが、急速な成長につながっていると感じています。
「困ったときはmadoguchi」を目指して

 小川
小川会社の雰囲気について教えてください。
福士さん:一言で表すと「自由でありながら熱量の高い」組織だと思います。現在40名ほどのメンバーがおり、この4月には新卒社員も9名ほど加わる予定です。
社内の特徴として、縦も横も距離感が非常に近いことが挙げられます。役職や年次に関わらず、ビジネスの場面では活発にコミュニケーションが飛び交い、ときにはプライベートな部分までお互いに理解し合っている関係性があります。
月間目標を達成した際には全員で飲みに行くこともあり、若くてエネルギッシュな雰囲気が社内には溢れています。ただ単に「楽しい」だけではなく、一人ひとりがしっかりと自分のビジョンや目標を持って努力している点も特徴です。
私たちの企業文化で特に大切にしているのは「自分の成長」と「事業への貢献」のバランスです。社員それぞれが「自分はどう成長したいか」を明確に持ちながら、同時に「このサービスをどう良くするか」という視点も持っています。周りの熱量に引っ張られて自然と前向きになれる、そんな環境だと感じています。
また、毎日の業務終了前の短時間ミーティングなど、PDCAを回す仕組みも定着しており、若手でも急成長できる土壌が整っています。そうした環境もあって、ここ1年は社員の定着率も大幅に向上しています。
 小川
小川これから入社される方に、特に求めていることは何ですか?
私たちが求めているのは、圧倒的な行動量とミッションへの共感です。そして採用では「お互いのミスマッチを防ぐこと」を最も重視しています。
採用プロセスでは、会社の実態を正確に伝えることを心がけています。「このビジョンのためにこれだけの覚悟で働いている」ということを率直に伝え、「社員は遅くまで働くことも多い」といった現実も隠しません。また、選考では複数の社員と話す機会を設け、会社の雰囲気や社員の人柄を十分に理解したうえで入社を決断してもらうようにしています。
具体的な人物像としては、まず「量をやりきる覚悟」が大切です。私たちはまだ発展途上の会社なので、圧倒的な行動量が必要になります。1日に何十件もの電話をかけることも日常的で、こうした「量」をこなす中でしかみえない景色があります。
もう一つは、私たちのミッションへの共感です。不用品回収や駆けつけサービスはまだ「よくわからない業界」ですが、私たちはそれを変え、「この業界といえばmadoguchi」と言われる存在になりたいと考えています。そういう挑戦に一緒に熱狂できる人を求めています。
実際、多くの方が「成長したい」という理由で入社を決めており、こうした共感をベースにした採用が定着率向上にもつながっています。

 小川
小川「よくわからない領域を変えたい」とお話しされていましたが、具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか?
福士さん:私たちが最も大切にしているのは、「プラットフォームと業者さんが一つの共同体になる」という考え方です。この業界は大手企業が全国展開しづらい構造になっています。たとえばエアコン修理や駆けつけサービスは地域性が強く、専門技術も必要なため、全国均一のサービスを提供するのは非常に難しいんです。
こういった背景から、私たちのような業者さんを束ねるプラットフォームが「共同体」として機能することが重要だと考えています。ただ「集客しますよ、頑張ってくださいね」というスタンスでは限界があるんですよね。
その問題を解消するために業者さんとの日常的なコミュニケーションを徹底しています。1日に100社以上の業者さんと話すこともあって、単なる取引先ではなく、一緒に成長していくパートナーとして関係構築を行っているんです。売上に直結しないコミュニケーションも大切にしていて、「最近どうですか?」「アプリの使い勝手はいかがですか?」といった会話を通じて、常に現場の声を吸い上げています。
ビジネスモデル自体も「売上折半型」にしています。「オヨビー」では業者さんの売上と私たちの収益が直結する仕組みにすることで、利害が完全に一致する関係性を構築しています。これで「業者さんが成功しないと、私たちも成功しない」という意識が社内に根づき、本気で業者さんの成長をサポートする文化が生まれました。
営業体制も工夫していて、契約を取った社員がそのまま継続してフォローする一貫担当制を採用しています。よくある「営業は契約だけ取って、その後は別のチームが対応」という分断を避けて、責任感と愛着を持って業者さんをサポートしています。
実はいま「オヨビー」のTシャツを作成して業者さん側に作業着として提供するという取り組みもはじめています。お客様からみて「オヨビー」の業者さんだとわかることで、サービスの質に対する信頼感も高まりますよね。
こうした取り組みはすべて「よくわからない業界」を変えるための基盤づくりなんです。私たちが目指しているのは、「困ったらオヨビー」と自然に思い出していただけるような、業界のスタンダードになること。そしてその実現には業者さんの質とサービスレベルの向上が欠かせないと思っています。
 小川
小川今後の展望を教えてください。
福士さん: 私たちは「〇〇といえば窓口」という考え方を大切にしています。つまり、各業界でサービスを探すときに最初に思い浮かぶ存在になることが私たちのビジョンです。
このビジョン実現のため、2027年の上場を目指しています。上場自体が目的ではなく、より多くの資金と社会的認知を得て、生活インフラ領域でより大きなインパクトを生み出したいと考えています。
上場までは、メディア事業・アプリ事業・CRM事業の強化に集中します。特にCRM事業は業界の構造的課題解決の鍵です。多くの業者さんが「その日暮らし」で長期的な顧客管理ができていない現状を変えるため、使いやすく手頃な業界特化型CRMツールを開発しました。
長期的にはフランチャイズ展開やM&Aも視野に入れており、私たち自身が業界に直接参入することも検討しています。不用品回収業やフロン回収業のノウハウ蓄積も進めています。
最終的に目指すのは、「困ったらとりあえずここに頼めばいい」という存在になること。そのためには単なる知名度向上ではなく、業者さんと一体となってサービス品質を高めることが重要です。一社一社の質を向上させることで市場全体を健全化し、「困ったときはmadoguchi」と自然に思い出される存在を目指しています。
| 法人名 | madoguchi株式会社 |
|---|---|
| HP | https://madoguchi.inc/ |
| 設立 | 2016年1月15日 |
| 事業内容 | ・WEBメディア事業 ・アプリ事業 ・RM事業 |
| 採用情報 | https://recruit.madoguchi.inc/home/ |
※2025年2月21日の情報です。