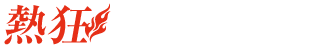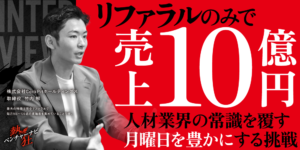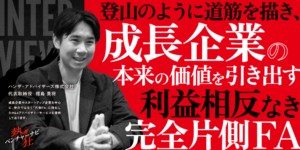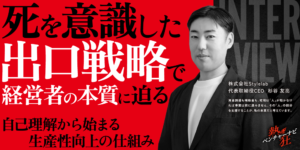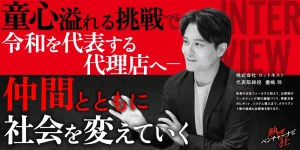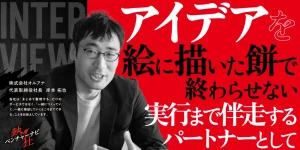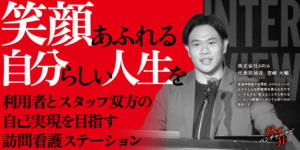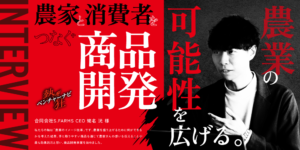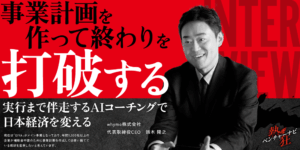【代表インタビュー】株式会社木下商会 代表取締役 村山 太一
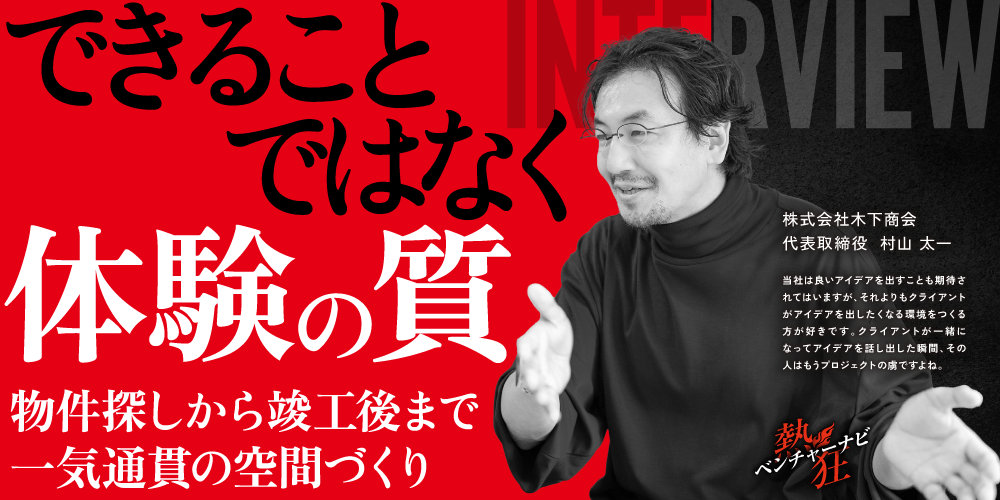
空間づくり×体験価値で描く新しいオフィスデザインの形
オフィスデザインの会社を選ぶとき、何を基準に判断するでしょうか。デザインの美しさ、価格、実績——多くの人がそうした要素で選ぶかもしれません。しかし、「できることにお金を払う人は少ない。体験の質が大切なんです」と語るのが、株式会社木下商会 代表取締役の村山 太一さん(以下、村山さん)です。
不動産仲介からオフィス設計、家具調達、ウェブサイト制作まで。村山さんが手がけるのは、空間づくりに関わるすべての体験を向上させる一気通貫のサービスです。その背景には、外資系家具メーカーの営業として数億円規模の案件を成功させ、前職では事業部立ち上げを経験した独自のキャリアがあります。
2019年、35歳で独立した際の資金はわずか50万円。子ども2人を抱え、住宅ローンを払いながらのスタートでした。しかし「成果がみえないと信用を失う」という強い信念のもと創業から今まで組織を拡大し続けています。「言われたことだけやっても成果は出ない。結果を引き寄せるまで行動する」—そう語る村山さんに、仕事への熱狂と会社づくりへの想いを伺いました。
プロフィール

株式会社木下商会
代表取締役 村山 太一
趣味
建築、旅行、散歩、漫画、ゲーム
座右の銘
同じ1なら、いい1がいい
尊敬する人
田中 角栄
学生が読むべき本
「論理哲学論考」ウィトゲンシュタイン
経営者におすすめの本
「精神現象学」G.W.F.ヘーゲル
人生で一番熱狂したこと
何事でも結果を出し続けること。少しずつでも、自分の力で社会を変えていくことを諦めない。
空間づくりの体験を最初から最後まで。不動産オーナーまで見据えた一気通貫のサービス

できることではなく、体験の価値を届ける
小川:御社がどんな事業をされているのか、教えていただけますか?
村山さん:「どんな事業をやっているか」と聞かれると、いつも困るんです。できることで言うと多くなってしまったので。
普通、会社はできることを1つに絞って専門性を打ち出しますよね。でも当社はそう考えて会社をつくっていません。クライアントさんからお金をいただくときは、できることに対価をいただくのではなくて、どんなサービスを通して経験した体験に応じてお金が動くことが重要だと思っています。
価値として感じてもらうときに大切なのは、体験が良かったと思えるかどうかなんです。当社は、空間をつくることに関わるすべての体験を向上させることを目指しています。具体的には、物件を探す不動産仲介から始まり、オフィスの設計・デザイン、家具の調達、そして完成後のウェブサイト制作まで手がけています。
事業用不動産は「交渉」が本質。代理人として体験の質を上げる
小川:不動産仲介も手がけられているとのことですが、どのような特徴があるのでしょうか?
村山さん:事業用不動産の仲介は、賃貸住宅とは性質が異なります。事業者同士のビジネスはすべて対等なので、毎回交渉するんです。だからこそ、交渉をしっかりサポートしない仲介業者には意味がありません。あくまでも代理人として振る舞うことが重要なんです。
また、私たちはデザインも手がけているため、現場で「この場所をどう使いたいか」「どうすればより良くなるか」といった視点で一緒に考え、ご提案することができます。こうした一連の体験こそが、私たちの強みだと思っています。
手続きが終わればすぐに使える状態をつくる
小川:オフィスの設計やデザインも手がけられているんですよね?
村山さん:はい。デザインをする際には、クライアントの組織や事業について深く理解する必要があります。そして当社では、家具の選定から設置まで対応しています。
よくある「家具はお客様でご用意ください」というスタイルだと、本当に狙っていた空間が実現できないことが多いんです。だから当社では、家具選びも含めて最後まで関わり、引き渡し時にはすぐ業務を開始できる状態まで仕上げることにこだわっています。
完成後の活用まで見据えたサポート
村山さん:さらに、オフィスをつくった後の活用も重要です。せっかく素敵なオフィスをつくっても、実際に足を運んでもらわなければみてもらうことはできません。でもウェブサイトに載せれば、いつでも誰でもみられる状態になります。
これは採用活動においても有効です。採用活動で「こんなオフィスで働けるんだよ」と伝えることは、どのような会社でもすごく大切ですよね。つくって終わりではなく、しっかり活用してほしい。そのためサイト制作もできるようにしています。
もう1つの事業として、不動産オーナー向けの広告ツール制作も手がけています。クライアントは不動産オーナーが持つ不動産に入居されるわけですから、オーナーさんも幸せにならないと、本当のビジネスとして完結しないと思っているんです。事業オーナーと不動産オーナー、両方の体験の質を上げていくことで、みんなが幸せになる循環をつくりたいと考えています。
クリスピー・クリーム・ドーナツに学ぶ——ブランドを感じる体験から「世界観」をつくるデザイン
「気取らないデザイン」をあえて取り入れる理由
小川:クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンさまのオフィスデザインなど、御社の実績を拝見したのですが、どういった特徴があるのでしょうか?
村山さん:今回意識したのは、彼らのブランドが社内にいかに浸透するかでした。トレンドに敏感な人だったらやらないようなベタな方法をあえて使っています。たとえば、彼らの商品はドーナツですが、ドーナツという軸は同じでも、実際の商品は時期やラインナップによって変わります。だから私はブランドの核は「箱」だと思ったんです。あの箱を開ける瞬間が一番ブランドを感じるのではないかと。
それで、あの箱をそのままオフィスの中に再現しました。会議室を箱型にして、ぐるっと回遊できるようにレイアウトしています。床にはドーナツ型のくり抜きも入れています。建築家や有名デザイナーならやらないような、親しみやすいデザインをあえて取り入れているんです。
選ばれる理由は「期待を超える」提案の姿勢
小川:そういった中で、御社を選ぶ理由として、どんなことがあげられますか?
村山さん:実は、できることで評価されて選ばれるより、うちは「提案の姿勢が良い」と言って、選んでくれる方が多いです。
このインタビューでも、ある程度答えを期待しながら来られますよね。でもそれを「これが答えかな」と思って話し始めたら、つまらなくなってしまいます。こちらも予想はするんですが、あえてそれを超えていく。期待を超えるというビジネスマインドが、メンバーにもしっかり根づいていることが、当社の強みだと思います。
仕事の楽しさに気づいた転機。東日本大震災後の地震保険査定で学んだこと

「言われたことを完璧にやる」では成果は出ない
小川:これまでお仕事をされてきた中で、熱狂したエピソードを教えていただけますか?
村山さん:「熱狂」というと、つらいことの方がたくさん思い浮かびます。ただ、1つの出来事というより、つらい経験を乗り越えたから次にチャレンジできて、という連鎖の積み重ねなんです。だから、あえてつらいことに挑戦し続けるようにしています。
小川:その中で特に印象に残っている出来事はありますか?
村山さん:私は高専から大学編入、大学院を卒業して、まあまあできるつもりで社会に出ました。でも実際はできなかった。最終的に希望する編集プロダクションに採用されましたが、入ったことに満足してしまい、仕事としては全然できませんでした。
言われたことを完璧にやれば良いというメンタリティだったんです。でもリーマンショックの影響で解雇され、天職だと思っていたのに自分には何もできないと気づかされました。社会を舐めていたんです。
仕事自体をクリエイティブにやるかどうかで価値が変わる
小川:それは大変でしたね。そこからどうされたんですか?
村山さん:東日本大震災の年、社会になかなか馴染めていない私は、惨めな気持ちでニュースを眺めていました。何かできないかと、もやもやしていたなか友達づてに地震保険の査定業務の話を聞き、思い切ってやってみることにしました。
仕事をしているうちに、相手への伝え方によって成果が全然変わることに気づきました。保険の仕組みそのものや、お金の流れ、政府の方針など、できる限りの情報を取り込んで、お客様への説明時に織り交ぜるようにしました。するとお客様から喜ばれるようになったんです。不安な状況の中で、周辺情報をしっかり伝えることで、お客様の不安を取り除けたんだと思います。
そこで分かったのは、カッコ良い仕事やクリエイティブな仕事があるのではなく、仕事自体をクリエイティブにやるかどうかで価値が変わるということです。クライアントのために価値が出ることを全力で考えてやる。
ただ言われたことを完璧にやろうと思っていた過去の自分はダメだなと思いました。そのメンタリティになってから、28歳くらいのときに「真面目に仕事をしよう」と思って営業職に就きました。
不可能だと思ったことはない。赤字のリスクを背負った大型案件の逆転劇

競合に遅れ、会社にモックアップの代金を自社で負担することを説得するところからスタート
小川:営業職に就かれた後は、どのようなことに挑戦されたんですか?
村山さん:真剣に営業の仕事に取り組もうと思い、輸入のオフィス家具の営業を選びました。1脚10万円近い椅子を300脚売るような仕事です。とあるプロジェクトで、担当者から話を聞いた時「ライバル会社はすでに提案をもってきている」と聞きました。みると、6席分のモックアップ(試作)がすでに組まれていて、この時点で2ヶ月くらい差がついていたんです。
せっかくお声をかけてもらったこともあり、そのチャンスは逃してはいけないとチャレンジすることにしました。早速ですが、6席分のモックアップを海外の工場でつくって飛行機で運ぶことにしました。これが数百万円かかります。まだプロジェクトは始まってないのに、会社にモックアップの分の赤字を背負ってくれと説得するところからスタートでした。
本国のトップを動かして逆転。最終的にほぼ全ての家具を受注!
小川:そこからどうやって逆転されたんですか?
村山さん:提案先の担当者の上司はライバル会社に肩入れしていて、なかなか口説けません。だったら、その上の決裁者を口説こうと思いました。
自社の本国営業部門の上層部に、提案先のアジアパシフィックのトップを説得してほしいと依頼しました。すると上層部が動いてくれて、本当に合意形成を得ることができました。最終的に全部ひっくり返して、約5億円の売り上げにつながりました。
結果を引き寄せるまで行動すること
小川:自ら仕事を取りに行く姿勢が印象的ですね。
村山さん:世界的な大企業の家具納品の仕事を取りにいったこともありますよ。先輩の仕事を「手伝います」と言って、夜な夜な残って働きました。その関係値があったので、その人が辞めるときに案件を丸ごと引き継ぐことができました。
みんなだってそうやって仕事を取っていけば良いのにと思うわけです。なぜ仕事が降ってくるのを口を開けて待っているのかと。それが29、30歳くらいのときでした。
仕事で不可能だと思ったことはありません。良い結果も悪い結果も出るものですが、悪い結果を恐れてやらない理由もありません。言われたことだけやっても成果は出ないので、それ以外も埋めて絶対結果を引き寄せるというやり方を始めてから、仕事が本当に面白く、好きになりました。
35歳で独立、50万円の資金からのスタート。徹底した結果へのこだわり

前職の事業部立ち上げでみえた「自分でやればできる」という確信
小川:そこから独立されるまでの経緯を教えていただけますか?
村山さん:営業系の会社でマネジメントを経験した後、15人くらいの規模のベンチャー企業に入社して事業部を立ち上げました。もともとオフィス仲介の会社だったのですが、私が新しくオフィスデザインの事業を立ち上げて、今ではオフィスデザインの会社にも見えるようになっていると思います。
もともとベンチャーに入った後は絶対独立しようと思っていたので、ある程度の経験を積んで独立しました。
目標は絶対に達成する「仕事のレベルの高さ」
小川:独立してからは順調でしたか?
村山さん:実は、開業時に50万円くらいしかなかったんです(笑)。その当時、子どもが2人いて住宅ローンも払っていたにもかかわらず。来月から収入があれば良いだろうと。不安はなかったです。自分でプロジェクトのハンドリングをして、数字を落としたことはほぼありません。成果にはこだわっています。
小川:村山さんにとって、「成果を出す」ことはどういう意味を持つのですか?
村山さん:立ち上げ時って、すでに業界で活躍している人たちからみられるんですよ、「この新参者、どんだけやるんだ」って。その人たちに「仕事ってこの程度でしょ」という低い基準で判断されるのが嫌なんです。
自分が考える仕事のレベルはもっと高い。それを信用してもらうには、結果を出し続けるしかありません。数字という明確な成果で示すことで、業界の空気を変えていく。だから目標を達成し続けることにこだわっているんです。
「プロジェクトに火を灯す」主役を増やす裏方という哲学

熱量ではなく「動きやすさ」をつくる摩擦ゼロ理論
小川:「プロジェクトに火を灯す」というコンセプトは、どのような想いが込められているのでしょうか?
村山さん:意外とみんな人は熱量で動くと思っていますが、私が好きなのは摩擦ゼロ理論です。動きやすいところをつくっていったら勝手に転がり出すくらいの感覚なんです。
だから火を「つける」のではなく、火を「灯す」なんです。「灯す」というのは道標を示すようなもので、先を照らすという意味です。熱烈なリーダーにはつい従いたくなってしまいますよね。従者は主役になれません。私は主役を増やしたいんです。
当社は良いアイデアを出すことも期待されてはいますが、それよりもクライアントがアイデアを出したくなる環境をつくる方が好きです。クライアントが一緒になってアイデアを話し出した瞬間、その人はもうプロジェクトの虜ですよね。
プロジェクトデザイナーとして会社自体を設計する
小川:そういった環境づくりは、社内に対しても意識されているんですか?
村山さん:そうですね。私の名刺には「プロジェクトデザイナー」と書いてあります。「きのもと商会」という会社自体をプロジェクトに見立てて、「プロジェクトに火を灯す」をコンセプトに掲げているんです。
会社の中で働いている人も自分で動いて、良い結果を出せる状況をつくっていくことが大切です。
結果にコミットする文化。失敗を認めて次に進む成長環境

努力の方向を間違えているから結果が出ない
小川:御社で働く場合、どのような成長や挑戦ができる環境があるのでしょうか?
村山さん:過去に何をやってきたか、どんな勉強をしてきたかはこだわりません。だけど結果にコミットできる人を歓迎します。
ダメだったら反省しなければいけません。失敗するときは、努力の方向を間違えているからダメなんです。ダメと認めないと努力の方法を変えられません。達成しようと思ったら、やり方を変えるしかないんです。
これを続けていると、打たれ強くなるし、現実に目を向けやすくなります。つらいですけど、抜け出すのは簡単です。
今の結果が失敗なだけで、全てを失敗したわけではありません。努力の方法の選択を間違えただけです。選択を変えれば良いんです。
環境とチャンスを提供する
小川:会社で働くメンバーとしては、どういう人に来てほしいと思われますか?
村山さん:私自身、環境があれば成果が上がると思っていた人だったので、「自分に足りなかったのはチャンスだけと思っている人」や「成果を出して社会を変えたい人」が来てくれると良いですね。チャンスはめちゃくちゃ与えられます。
小川:「社会を変えたい人」とのことですが、具体的にはどういうイメージでしょうか?
村山さん:社会を変えるというのは決して大きなことばかりではなく、目の前のお客様を幸せにすることもその一歩だと思っています。プロジェクトの中で言うと、営業のように前面に出て変えていく姿勢というよりも、環境を整理したり状況をうまくファシリテーションすることで、物事をグッと前に進めるのが当社のスタイルです。
こうした振る舞い方は、今まで明確に「仕事」として指示されたことがない人も多いと思いますが、こういうやり方で社会を変えていくことに面白さを感じてくれる人に来てもらえたら嬉しいですね。
100人の自立した人材が支え合う会社へ。パワフルな組織を目指して

職人技で終わらない、新陳代謝のある組織づくり
小川:会社の雰囲気や、どういった人が多いか教えていただけますか?
村山さん:社員は内向的な人が多いです。細かいことに気づいたり、良い意味での繊細さがあるというプラスの意味もあります。ただ、クライアントに火を灯してプロジェクトをリードしていくには、もう一歩力強さがあると良いなと考えています。
状況はまだまだ良くなると思っています。もう少し気合の入った、裏方ができる人がいると良いですね。これを言語化すると、自分の意志を通してでも環境を変えたり、結果を変えていこうという意志がある人です。
小川:今後、どのような会社にしていきたいですか?
村山さん:ナイーブさとガッと動かすパワー、両輪が必要なので、そちらを上げていくようにメンバーを増やしていきたいです。
クライアントワークの会社は、ついつい職人技的になって少人数で収まることが多いです。でも私はそれは不健全だと思っています。ずっとパワフルな会社でありたいので、100人以上いるような状況にしたいです。自立的な人たちが100人いて、お互い支え合っている状況が良いですね。
強みのある人間が100人集まれば潰れない会社になります。そこからずっと時代を越えて残っていく会社にしたいと思っています。
いつかプレイヤーに戻りたい。自分を雇用してくれる会社へ
小川:100人規模の会社を目指されているんですね。村山さんご自身は、どのような立場を目指されていますか?
村山さん:私は死ぬまで働くつもりでいます。最終的にはプレイヤーに戻りたいので、自分を雇用してくれる会社に育てようと思っています。
プレイヤーの方が楽で良いですから(笑)プロジェクトだけ見れば良い。経営は全部見なければなりません。今は自分より上手くやる人がなかなかいないので、代わりにやっておこうという感じです。
会社概要
| 会社名 | 株式会社木下商会 |
| HP | https://kinomoto-firm.co.jp |
| 設立 | 2019年1月 |
| 事業内容 | ワークプレイスのデザイン・設計・内装工事 プロジェクトのマネジメント 不動産の仲介 不動産の広告制作(CG・VR・映像) メディアの企画・運営 Webサイトの制作 家具の販売 |
| 採用情報 | https://www.wantedly.com/companies/kinomoto-firm |
※2025年10月9日時点の情報です。