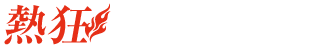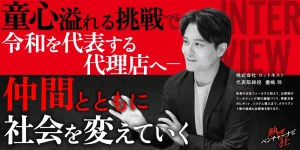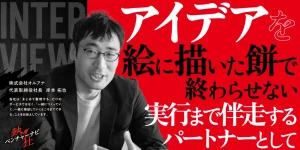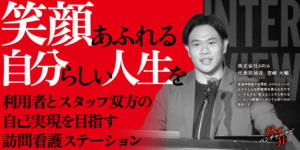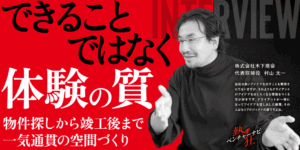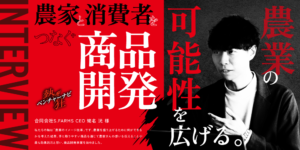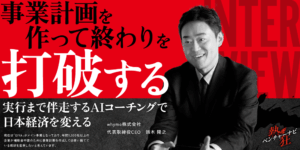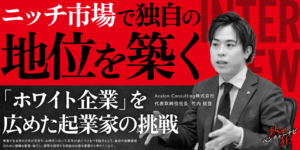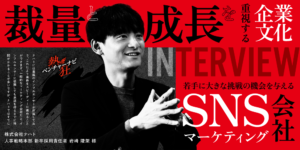【代表インタビュー】株式会社Anfini 代表取締役 橋本 純

近年、企業におけるシステム導入は、業務効率化の枠を超え、経営そのものを再構築する契機となりつつあります。クラウドの普及に伴い、「業務に合わせてシステムを設計する」から、「システム標準に業務を適合させる」流れへと大きく転換。いまやシステム導入は、単なるIT施策ではなく、経営戦略と直結するテーマとして位置づけられています。
こうした変化のなかで、株式会社Anfiniは、経営戦略の立案からシステムの導入・運用までを一貫して支援。経営の“コア”を的確に捉え、戦略とITを融合させることで、企業の持続的な成長を支える仕組みを描いています。
本インタビューでは、戦略コンサルティングを起点とする同社のアプローチを軸に、コンサル業界に潜む構造的課題、組織づくりの理念、さらには「ストックビジネス」への展望まで─ 代表取締役・橋本 純さんにお話を伺いました。
プロフィール

株式会社Anfini
代表取締役 橋本 純
趣味
仕事、サウナ(PC/スマホから離れて仕事のことを考えられるため)
尊敬する人
漫画『HUNTER×HUNTER』のクロロ
座右の銘
己に向き合い 人を想う
学生が読むべき本
「生き方」稲盛 和夫
人生で一番熱狂したこと
仲間やお客様のことを想いながら成果に向かって取り組んでいるときに、熱狂します
経営を動かす、“戦略×システム”の次世代コンサルティング

 小川
小川御社の事業内容について教えてください。
橋本さん:当社は経営コンサルティングを手がけています。経営コンサルティングと一言で言っても実は幅広い領域があって、私たちは上流から下流まで幅広く対応しているんです。
上流とは、いわゆる経営戦略を立てる部分を指し、下流はITの導入から運用保守までの工程です。当社は、この上流から下流までを一貫してサポートする、いわゆる総合コンサルティング会社です。
通常、コンサルティング会社は特定の領域に特化することが多いのですが、当社の経営陣はもともと総合コンサルティング会社に在籍していた経験を活かし、戦略立案からIT導入、そしてその運用保守までを包括的に手掛けています。
 小川
小川どんな企業がどんな課題でAnfiniさんに相談されることが多いのでしょうか?
橋本さん:私たちのお客様は、主に大規模なITシステムの導入を検討している企業が多いですね。こういったシステム導入って数十億円かかることもあるので、主に大企業から中規模の企業さんが対象になります。そういった企業さんが将来のシステム導入を見越して、経営戦略の策定や経営思想の転換といった、経営の根幹からご相談いただくケースが多いです。
基幹システムというのは、企業の決算を成り立たせる根幹となるシステムです。たとえば、日々の会計処理として領収書を登録して経費を計上したり、請求書を登録して売上を立てたりする、そういった売上と費用の両方を扱うシステムなどが含まれます。SAPやOracleといった、上場企業でも導入されている高機能でセキュリティの高いシステムがこれにあたります。
こういったシステムは、会社の規模が大きくなってくると必要になることが多くて、特に上場を目指す企業にとっては、このシステムが入っていないと上場の審査やセキュリティ面での監査が通らないこともあるんです。そのため、上場を検討し始めたくらいのタイミングで「導入しておこう」となる企業さんが多いですね。
 小川
小川企業ごとに異なるニーズにはどのように対応されていますか?また、近年のシステム導入における変化や傾向についても教えてください。
橋本さん:たとえば、クラウド会計ソフト「freee」のようなシステムでも、会社によって「使いやすい機能」と「使いにくい機能」があるんですよね。自社の業務にうまくフィットしない部分をどのように調整するか、または開発するかを検討するのが導入時の重要なポイントです。
これまでは企業の業務に合わせてシステムをカスタマイズすることが一般的だったんです。でも今は「クラウドパッケージ」というインターネット上で利用するシステムが普及してきて、セキュリティや安定性を確保するために、システムを大幅に変更することが制限されるようになってきました。
特にSAPやOracleといった大手のシステム提供会社は「システムを変えるのではなく、標準機能をそのまま使ってください」という方針を出しているんです。このような変化によって、システム導入の意味合いが大きく変わってきました。
以前はシステムを企業の業務に合わせていましたが、今は「システムを理解することによって経営を転換させる」という発想が求められるようになったんです。つまり、単に「ツールを入れるだけ」の話ではなく、システムを導入するなら経営戦略を理解し、場合によっては業務のやり方そのものを見直す機会になっているんです。
今はシステム導入がすごくチャレンジングでやりがいのある仕事になっています。システムを通じて企業の経営戦略自体を進化させ、成長や変革に直接貢献できる点が特に面白いと感じますね。「システムに合わせて業務を変える」という新しい時代の流れの中で、会社の未来を一緒につくっていけることが、この仕事の大きな魅力だと思います。
“制約”が問う、戦略とシステムの真価

 小川
小川システム導入を通じて、企業の目指す姿や大切にしている価値観をどのように実現しているのでしょうか?
橋本さん:企業がシステムを通して大切にしている価値を実現するために、必ずしもシステムを大きく変える必要はないんです。大切なのは、企業が「大事にしていること」や「目指している想い」をしっかり理解して、それをシステムを活用してどう実現するかを一緒に考えることです。そのためには創造力、理解力、共感力が必要になってきます。
まずは「どんな目標を達成したいのか」をお客様から丁寧にヒアリングします。その上で、その目標がシステムの機能で対応できるかを見極め、もし実現が難しい場合には「では、別の方法でどう解決できるか」を一緒に考えていくんです。
 小川
小川具体的に、どのようなケースでシステムの工夫が活かされたのでしょうか?
橋本さん:ある企業では、従来使っていた経営指標(KPI)を新しいシステムでも使いたいという要望がありました。ただ、導入したシステムがグローバルスタンダードな仕様だったため、以前と同じように特定の指標を管理するのが難しい状況だったんです。
そこで、私たちは経営陣と丁寧に話し合って、「その指標は本当に必要なのか」「経営判断に実際に役立っているのか」を見直しました。結果として、実は経営層が重視していない指標だったことがわかり、それによって不要な業務を削減できたんです。
もちろん、すべてのケースで指標を削減できるわけではありません。どうしても必要な指標がある場合は、システムの制約を踏まえた上で代替手段を考えます。たとえば、「一人あたりの売上」を直接確認する機能がないシステムでも、売上データと従業員数データを組み合わせて計算することで、大まかな傾向を把握できるようになります。
分かりやすくお話しすると、私たちのようなコンサル会社では「一人のコンサルタントがどれくらい売上を上げているか」というのは経営者として気になるポイントなんです。これがシステム上で直接みられなくても、売上の総額を従業員数で割ることで傾向は把握できます。バックオフィスの人数なども含まれるので完全に正確ではないですが、大体の傾向がわかれば経営判断はできますよね。
システム導入後は、業務効率が上がるだけでなく、社員間の「共通言語」が増えてコミュニケーションがスムーズになったという声も多いですね。また、目標や進捗が「みえる化」されることで、社員一人ひとりが自分の役割をしっかり理解できるようになります。結果として会社全体がチームとして動けるようになり、みんなのモチベーションも上がります。
このように、システムに限界があっても、ちょっとした工夫やアイデアで企業の課題を解決できるのが、この仕事の面白いところだと思います。
 小川
小川他社でもツールの導入は可能だと思いますが、御社が選ばれる理由や強み、特徴を教えてください。
橋本さん:システム導入において、これまではシステムをどんどん変えていく開発力や知識がITコンサルタントに求められていました。しかし、先ほどお話ししたように、今はシステムを大きくいじれない状況に変わってきています。そのため、求められるスキルも「既存システムに基づいて業務や経営を変革する力」や「戦略を構築する力」にシフトしてきているんです。
こうした変化の中で、戦略を立てる力のあるコンサルタントは、これまでの業界にはあまり多くいませんでした。一方で、私たちはもともと戦略コンサルタントとして立ち上げた会社です。そういった戦略を立てる力を強みとして持ちながら、そこからシステム開発の領域にも参入してきました。この背景が他社にはない私たちの強みで、お客様からも評価していただいているポイントだと思います。
“想い”から始まる組織設計 ― 人と戦略が共創する場所

 小川
小川起業した経緯や、経営において大切にしている価値観を教えてください。
橋本さん: 私はもともと大手のコンサルティング会社で働いていました。この業界には魅力を感じていたのですが、一方で高ストレスや長時間残業、厳しい指導など、長く働き続けるのが難しい環境でもあったんです。
実際、この業界では3年ほどで半分以上の人が辞めてしまうんですよ。その結果、3年以下の経験しかないコンサルタントばかりになってしまい、お客様にとっても最適なサービスを提供できていないのではないかと感じていました。
そういった状況を変えるために、「実力を伸ばしながらも、長く働ける環境をつくりたい」という思いで独立しました。この思いが当社のミッションにも込められていて、私たちは実力主義を保ちながらも、従業員が持続的に成長できる会社を目指しています。
当社のミッションは「お客様がもつ無限の可能性を引き出し、末永く発展していけるよう貢献する」です。ただ、ゴールを設定するだけでなく「どのように達成するか」というプロセスも重要だと考えています。一般的なコンサルティング会社はソリューションやプロダクトベースで考えることが多いのですが、私たちは組織のあり方や、そこで働く人々の感じ方にも注目しているんです。
 小川
小川御社では、どのようなキャリアの選択肢が用意されていますか?
橋本さん:当社の従業員の約8割はコンサルタントとして活躍していますが、私たちの提供する業務は一般的な経営コンサルティングだけにとどまりません。現在はコンサルティング会社としての形ですが、将来的には企業の経営支援を行う事業会社へとシフトしていきたいと考えています。
実際には、全体の7〜8割がコンサルティング業務で、残りの約3割は経営支援のための業務になります。具体的には教育事業の推進、ビジネス系メディアの運用、新規プラットフォームサービスの立ち上げなど、多岐にわたるプロジェクトに取り組んでいます。
私たちが目指す「経営支援」とは、コンサルティングに加えて、システムやツールの開発、SaaSサービスの提供など、お客様のニーズに応じたサービスを包括的に提供することです。これを「コンサルティング+サービス」という形でお客様に価値を届けていきたいんです。
キャリアパスとしても、コンサルタントとしての経験を積みながら、経営支援の分野にも挑戦できる環境があります。事業に深く関わったり、会社の経営に携わる機会も豊富にあるんですよ。私たちは「選択肢の豊富さ」を幸福の一つの要素だと考えていて、社員一人ひとりが自分にとって最も幸せに感じるキャリアを選べるようサポートしています。
コンサルタントとして専門性を極める道もありますし、私のようにコンサルタントでありながら経営者としての役割にも挑戦できる環境も用意しています。また、成果を出したり、リーダーシップを発揮した方には、リーダー層や経営層として早い段階から会社の経営に携わってもらうこともあります。

 小川
小川これから入社される方に一番求めることは何ですか?
橋本さん:私たちが求めるのは、スキルや即戦力としての実力ではないんです。私が最終面接で見ているのは「人としての成長力」です。
昔、本で読んだ話なんですが、人と樹木の成長プロセスには共通点があると感じています。植木屋さんのような樹木を植える専門家は、若い木がどれほど立派に成長するかを見極められるそうなんです。その秘訣は「根」にあって、花が美しく咲き誇る木というのは、地上に伸びる前に根がしっかりと太く広がっているんです。つまり、根がしっかりしている木ほど、枝葉もバランスよく伸びて、やがて美しく咲き誇るわけです。
人で考えると、この「根」にあたる部分が「人間性」だと思っています。学生時代の知識や経験が少なくても、人を思いやる心や豊かな人間性を持っている人は、その後のビジネスでの成長や成功が期待できるんじゃないかと考えています。
実際、私が新卒で入社したコンサルティング会社でも、当時の同期で、スキルはまだ未熟でも人間性が豊かだと感じた人たちは、みんな何かしらの成果を残していました。
人間としての「器」や「心の広さ」は、若い時点ですでにある程度形成されている部分が大きいと思うんです。今後、それをどうビジネスに活かしていくかが、成長のカギになると考えています。
 小川
小川今後の展望を教えてください。
橋本さん:現在私が目指しているのは、私の手を離れても企業の経営が自律的に成り立つ組織をつくることです。優秀なメンバーが揃いつつある今、私の影響を受けずに会社がどのように成長していくのかを見届けたい ─ そんな夢を追いかけています。
私の理想の会社像として「ロールモデル」にしているのが、漫画「HUNTER×HUNTER」に登場する「幻影旅団」の組織理念なんです。
幻影旅団は、上下関係がない中でも、お互いに役割や組織のミッションに対して忠実で、信じて任せ合う信頼関係が構築されています。また、幸福を追求する中でも最低限のルールをしっかり定義し、メンバー全員がそのルールを守る姿勢が息づいています。こうした点は、私が目指す組織文化と合致しているんです。
特に仲間同士が思いやりを持ち、目的に向かって結束して動ける姿勢や、リーダーがいなくても組織が機能し続ける柔軟性を持っていることも特徴的だと思います。
こうした組織観を基盤に、今後は「ストックビジネス」への転換を目指しています。従来のコンサルティングサービスは「フロービジネス」と呼ばれ、労働時間に対して報酬を得る形態です。この形式だと、私がいなくなればその分の損失が生じてしまいます。理想は、たとえば自動販売機のように、人が常時張り付かなくても自律的に価値を生み出し続ける仕組み。オーナーが稼働し続けなくても、サービスそのものが継続的な価値提供と収益を可能にする状態を目指しています。
SaaSやビジネスツールといった仕組み化されたサービスを、コンサルティングと組み合わせて提供することで、持続的な収益モデルの構築を目指しています。これにより、私自身の関与がなくても、企業が自律的に成長・運営できる体制を実現したいと考えています。
| 法人名 | 株式会社Anfini |
|---|---|
| HP | https://anfini-group.com/ |
| 設立 | 2021年5月7日 |
| 事業内容 | ・コンサルティング事業 ・エデュケーション事業 ・インキュベーション事業 |
| 採用情報 | https://anfini-recruit.net/ |
※2025年2月18日の情報です。